|
Latvian Voices 日本ツアーを聴く ガイスマ指揮者 佐藤 拓

写真は軽井沢国際合唱フェスティバルFacebookからシェア【HP編集室】
 8月、軽井沢国際合唱フェスティバル(主催:耕友会)の特別招待団体として、ラトヴィアから6人組女声ヴォーカルグループ“Latvian Voices”が初来日した。一部のラトヴィア音楽ファンには以前から知られていた実力派グループであるが、来日決定前まで日本での知名度はほとんどゼロに近かった。 8月、軽井沢国際合唱フェスティバル(主催:耕友会)の特別招待団体として、ラトヴィアから6人組女声ヴォーカルグループ“Latvian Voices”が初来日した。一部のラトヴィア音楽ファンには以前から知られていた実力派グループであるが、来日決定前まで日本での知名度はほとんどゼロに近かった。
彼女たちはリガの大聖堂合唱学校(Rīgas Doma kora skola)の出身であり、またメンバーの何人かは女声合唱団“Dzintars”にも所属していた。いずれも、ガイスマおよび音楽協会が親交を結ぶ指揮者アイラ・ビルズィニャ(Aira Birziņa)女史が指導しており、彼女たちとの浅からぬ縁を感じさせてくれる。 筆者は、彼女たちの最初の公演である川口での演奏会にガイスマ指揮者として、また最終公演である軽井沢には同じく招待団体の一つであったシグナス・ヴォーカル・オクテットのメンバーとして参加し、8日間の間に三度彼女たちの演奏に触れることができた。8月20日の川口と28日の軽井沢のプログラム内容はほぼ同一なので、印象的だった作品を中心に、彼女たちのコンサートを振り返ることにしよう。 コンサートの冒頭、メンバーが一人ひとり歌いながらステージ上に現れ、鳥の声、風の音、葉のざわめきなど自然の音を模した即興的な音響に包まれる。ソプラノのLauraによって突然導き出されたのは”Pļavas dziesma”、圧倒的な力強い歌声にまず度肝を抜かされた。民謡と自然が不可分なものである、ラトヴィアらしい美しいアレンジであった。 コンサートの前半はすべてラトヴィア民謡のアレンジで、その多くはメンバーのLauraとNoraによって書かれている。このグループの最大の特徴ともいうべきはその音域の広さで、特に2人のアルトAndraとMaltaはほぼ男声のバリトンの音域までをカバーする驚きの低音の持ち主。この特徴的な音域をフルに活用する独自のアレンジによって、メンバー1人1人の魅力が存分に発揮されているようだった。 “Rūtoj’ saule”ではMaltaの強烈な地声発声が、まるで男性歌手の朗々たるアリアのように鳴り響く。クラシック的な発声と民謡的な地声発声を自由自在、瞬発的に使い分けるそのテクニックには舌を巻くばかりだった。もはや帰ってくることのない恋人を歌った悲しい民謡”Es gulu gulu”では、メゾソプラノのElinaの魂をふりしぼるような絶唱に、こみ上げる感動を押さえることができなかった。この曲への観客の没入は、プログラムの中で随一であったと思う。”Ganu dziesma”は前半のプリミティヴなアレンジと後半の柔和でポップなアレンジの対比が実に美しく、Andraの柔らかな低音の歌唱が非常に印象的だった。 曲中彼女たちは自らパーカッションを奏でており、曲がった流木のようなものに金具を取り付け、地面を打ち付ける錫杖のような謎の楽器は特に目を引いた。なんといっても彼女たちの衣装が美しい。アクアグレイと琥珀色を組み合わせた、メンバーごとに違った形状の個性的なデザイン。琥珀はラトヴィアの特産で、かつラトヴィア民族にとって非常に象徴的なものである。彼女たちの歌と同じように、衣装においても民族的なものと現代的なものを自然な形で融合させようというコンセプトがはっきりと見て取ることができた。 プログラムの後半は、宗教音楽から始まったが、これがまた独創的で、彼女たち曰く「民謡ミサ」というその作品は、ラトヴィア民謡の伝統と、学校で習うようなクラシック音楽の伝統という二つの軸を統合するための試みであるという。演奏されたGloriaとSanctusはラテン語のテキストを用いながら、民謡のアレンジで見せた自由な発想と力強い発声を随所に用いて、唯一無二の音世界を表出していた。Sanctusのテーマを歌うZaneの美声も強く印象に残った。 日本をはじめ世界的人気の作曲家Ēriks Ešenvaldsの大ヒット作である”O Salutaris Hostia”は、LauraとNoraの超絶に美しいデュオに心が洗われるようであった。Lauraは民謡・ポップス的な歌い方の似合うソプラノだが、Noraは対称的に非常に美しいクラシックの発声で、その対比もまたこの曲の美しさを引き立てていた。 プログラムの最後には楽しげな振りや演技の付いたクラシック・メドレーに続き、今回の日本公演のために書き下ろした「上を向いて歩こう」のアレンジ、L.コーエンの”Halleluja”で締めくくられた。エンターテインメント性まで兼ね備えたその多才・多彩ぶりに、最後まで魅了されつくした1時間だった。 彼女たちのアンサンブルには「歌」のもつ根源的なエネルギーがあふれていて、特にラトヴィア民謡を歌うとき、そこには民族的な背景だけでなく、現代を生きる彼女たち自身のパーソナリティーが重ねられて、実にアクティブな音像となって立ち上がっていた。(個人的な話だが、日本の民族的なものをどう現代の音楽の中に投影していくか、ということは私自身の最大の関心事であり、彼女たちの歌から得たインスピレーションは計り知れない。) 強烈な感情の発露や訴え、旋律美の光るラトヴィア民謡の数々だが、彼女らの演奏には、ラトヴィア語を十全に理解しなくても感じ取ることのできるユニバーサルな感動があった。ユニバーサル、と言いながらそのサウンドは非常に民族的で個性的。究極的にはグローバルたりうるものは、すべからく深くローカルに根差しているべきものである、という、ある指揮者の教えが脳裏に浮かぶ。 彼女たちのMCの中に、「哀しみを尊び、喜びと哀しみが表裏一体となっている、という感覚では日本人とラトヴィア人は近しいのかもしれない」というコメントがあったが、おそらくそれはまったくの正解で、しかもそれは彼女たちが思っていた以上に日本人の胸を打つものだったに違いない。 メンバーのNoraに日本の合唱団の印象を聞く機会があって、彼女によれば、演奏のレベルは極めて高いが、「合唱団」と「アンサンブル」の区別がないことに違和感がある、とのことだった。合唱団が歌うような曲はアンサンブルでは演奏しないし、その逆もまたしかり。音楽のスケール感や声の出し方も違ってくるし、アンサンブルを名乗っていながら指揮者が前に出てくることもあり得ない、という。日頃少人数でのアンサンブルに精を出す筆者としてはまったく同意することで、まだまだ「アンサンブル」独自の楽しみ方が日本では開拓しきれていないのかもしれない、とも感じた。 同じ招待団体として3日間軽井沢にいたものの、それぞれのスケジュールが多忙で、彼女たちと直接触れ合える時間は非常に少なかったのが残念だった。ただ、アイラ・ビルズィニャがガイスマ・音楽協会宛てに彼女たちに預けてくれたラトヴィア土産は無事受け取ることができた。写真を撮り損ねてしまったが、『百万本のバラ』の原作曲者Raimonds Paulsの写真がパッケージに印刷されたおいしいチョコレートで、先日のガイスマの練習で団員とシェアすることができた。 Latvian Voicesは近い将来の再来日を熱望しているそうだ。 ラトヴィア音楽のまことの美しさ・奥深さと、彼女たちの歌声の感動を再び味わえる日を心待ちにしたい。 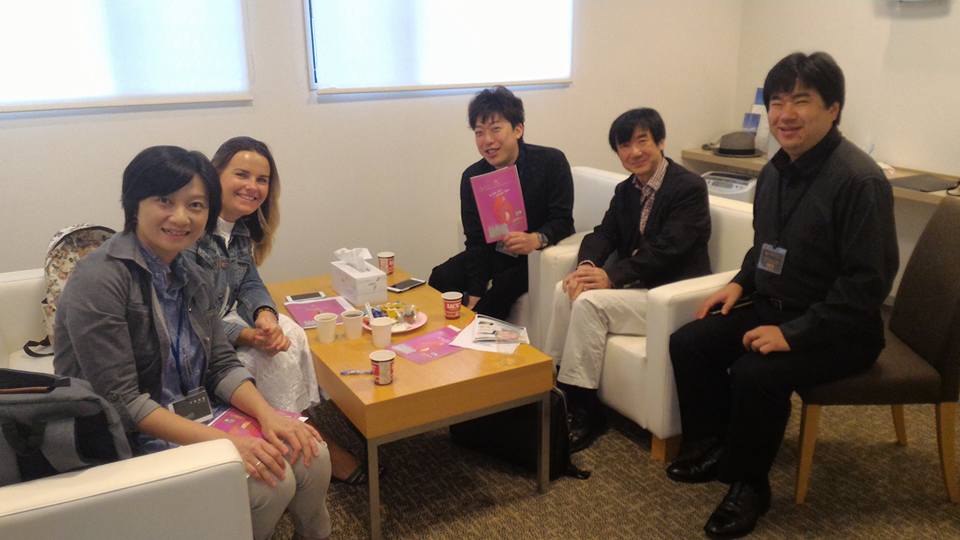
写真は軽井沢国際合唱フェスティバル・アンサンブルコンテストの審査員打合せスナップ(左側奥の女性がNoraさん) )
|


 トピックス
トピックス  2016年9月のニュース
2016年9月のニュース  【9月16日】Latvian Voices 日本ツアーを聴く
【9月16日】Latvian Voices 日本ツアーを聴く