ウィーン古典派の系譜25「ビーダーマイヤーの時代」
前田二生氏のライフワーク、限りない価値と功績
(写真提供:前田二生事務所)
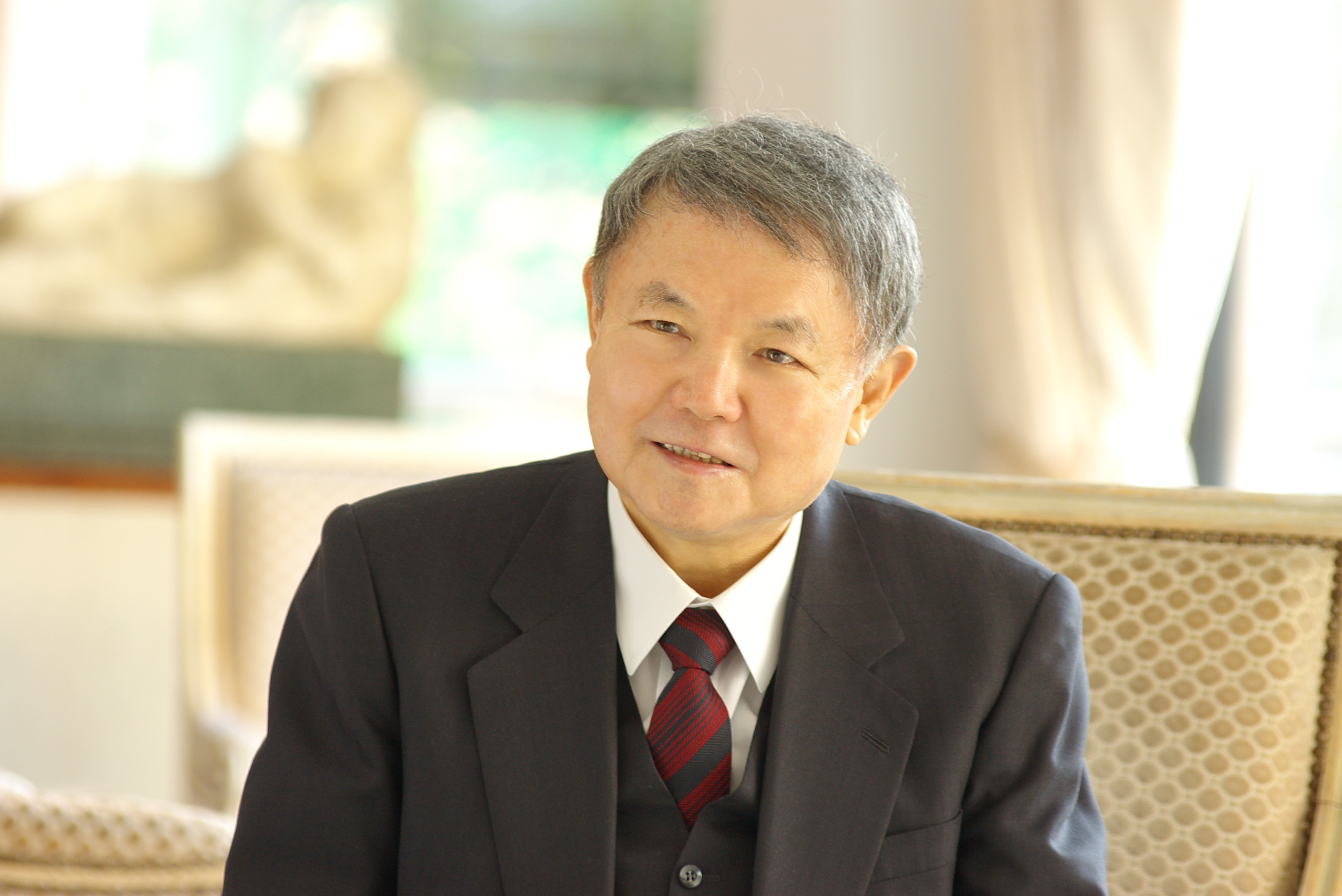 前田二生当協会会員が常任指揮者を務める新東京室内オーケストラの第25回定期演奏会を聴いた(5月19日・紀尾井ホール)。1990年に開催した第1回演奏会から毎回、「ウィーン古典派の系譜」と題して、ひたすらウィーン古典派の流れをくむ作品を紹介し演奏し続けた功績は限りなく大きく、称賛に値するライフワークと言えよう。背景にウィーン楽友協会資料館館長ビーバ博士と前田氏の強い絆があった。
前田二生当協会会員が常任指揮者を務める新東京室内オーケストラの第25回定期演奏会を聴いた(5月19日・紀尾井ホール)。1990年に開催した第1回演奏会から毎回、「ウィーン古典派の系譜」と題して、ひたすらウィーン古典派の流れをくむ作品を紹介し演奏し続けた功績は限りなく大きく、称賛に値するライフワークと言えよう。背景にウィーン楽友協会資料館館長ビーバ博士と前田氏の強い絆があった。
今回は、ウィーンでも極めて特徴的な19世紀の約30年間に生まれたシューベルト、ベートーベン、ヨハン・シュトラウスⅠ世、パガニーニの作品に焦点を集めた内容で、とりわけ興味深かった。この日のプログラムにビーバ博士が寄稿した解説によると、ピーターマイヤーと呼ばれるこの時代は、フランス革命にはじまるヨーロッパの戦乱がウィーン会議(1815年)でやっと終結した後の約30年間で、まだ警察が厳しい監視体制を続けるなど混沌としていた。こんな中で音楽愛好家は警察の監視下で開かれるコンサートより、一般家庭に客を招いて自由な雰囲気で演奏を楽しんだ。ソロや室内楽はともかく、オーケストラの場合は、充分なスペースを確保するために、客は演奏の部屋の中のみならずトアを開放して隣室にまで広がって座ったり立ったりして聴いたという。作曲家たちはコンサートホールのためではなく、こうしたプライベイトな集まりの為に作曲を続け、これらがピーターマイヤー時代の音楽と呼ばれる。後世、コンサートホールではあまり演奏されない由縁でもある。
19世紀にタイムスリップした気分
この夜、客席を埋めた聴衆はこんな背景を熟知していた。私自身も、19世紀にタイムスリップして、あたかも当時一般家庭で行われていたサロンコンサートのアットホームな雰囲気の中で音楽の素晴らしさを満喫した気持になった。オケのメンバーはそれぞれが一流の演奏家で紀尾井ホールに響くアンサンブルは何とも心地良かった。大ホールで開かれる大オーケストラの演奏会とは全く違った親近感と心豊かさを味わった。丹精で折り目正しい指揮を続ける前田氏との深い信頼関係がひしひしと伝わってきた。メロディーラインが何とも美しく奏でられた。聴衆の表情も良い音楽を満喫できた満足感がみなぎっていた。
演奏ではパガニーニのバイオリン協奏曲2番「ラ・カンパネッラ」と、シューベルトの第5交響曲が秀逸だった。イタリアのバイオリニスト・パガニーニは1828年、まだ取得困難だったパスポートを手にしてウィーンにやってきた。その並外れた演奏にウィーン人は驚嘆し大歓迎した。この第2番はウィーンの演奏会の為に作曲された、まさしくピーターマイヤー時代の音楽である。パガニーニの人気ぶりは、この日演奏されたヨハン・シュトラウスⅠ世のワルツが「パガニーニ風」と名付けられ、有名な“鐘のロンド”をワツルに編曲したものであることからも伺える。
この演奏ではソリスト・藤原浜雄氏のバイオリンを特筆したい。難曲を難曲と感じさせない見事な入魂の演奏だった。読響の首席ソロ・コンマスだが、ジュリアード音楽院留学時代の72年に、20世紀屈指のバイオリニスト・ミルシュタインの代役を務めて大喝采を博したエピソードも残す。
シューベルトの5番交響曲は、演奏者を木金管4、絃24名に減らして演奏された。要するに一般家庭で演奏出来るように作られた4楽章。シューベルトらしい美しいメロディーが続く佳品を爽やかに演奏した。この作品を聴けただけでもここに来た価値があった。
他の演奏曲はシューベルトの序曲、ベートーベン「アテネの廃墟」(かつてピアノで弾いたトルコ行進曲のオケ原曲が含まれていた)など。
同じプログラムを6月14日にウィーン楽友協会で演奏
前田氏は同協会主催の「ウィーン芸術週間コンサート」などの演奏会に21年連続出演しているが、今回も同氏が常任指揮を務めるスロバキア国立ジリナ室内楽団を率いて演奏する。なお。第26回定期演奏会は来年(2011年)4月13日(水)紀尾井ホールでの開催が決っている。当然、ウィーン古典派の系譜を追い続ける。
【Latvija編集長 徳田浩】